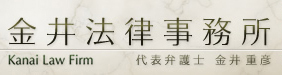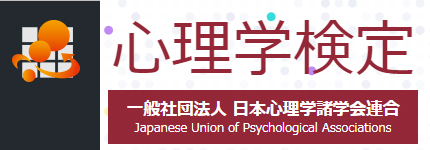楊 帆
楊 帆
[所属]
早稲田大学大学院文学研究科心理学コース博士後期課程
[研究課題名]
社会認知的マインドフルネスの視点からみる愛着スタイルの改善
研究概要(「研究計画書」より,一部略)
既存の愛着スタイルの介入プログラムは人間関係や他者の役割に焦点を当てており,コストとハードルが高い。本研究では,社会認知的マインドフルネスの視点に基づき,セルフコーチングで愛着スタイルを促進する試みを行う。研究1では質問紙調査を実施し,交差遅延モデルで社会認知的マインドフルネスが愛着スタイルに及ぼす影響を検討する。研究2では社会認知的マインドフルネスに基づくセルフコーチングで愛着スタイルを促進する介入の効果を検証する。
 西堀 まゆ
西堀 まゆ
[所属]
桜美林大学大学院 国際学術研究学位プログラム心理学研究領域博士後期課程
[研究課題名]
心理臨床家のキャリア形成過程におけるキャリアレジリエンスに関する研究:複線経路等至性アプローチによる分析
研究概要(「研究計画書」より,一部略)
本研究では,仕事上でネガティブな経験をしたにもかかわらずそれを乗り越えている心理臨床家のキャリア形成過程を,キャリアレジリエンスに注目して分析し,類型化することを目的とする。方法は複線経路等至性アプローチ(TEA)の理論を用いた半構造化面接とし,心理臨床家(公認心理師・臨床心理士の資格保持者)に対し大学入学時から現在に至るまでの経路を聴取する。
 下條 朝也
下條 朝也
[所属]
コニカミノルタ株式会社
[研究課題名]
パッケージデザインにおけるブランドらしさの知覚メカニズム: 深層学習を用いた暗黙的視覚特徴の検討
研究概要(「研究計画書」より,一部略)
本研究では消費者が特定の商品パッケージを見て「このブランドらしい」と認識する際の知覚メカニズムの解明を試みる。その際,深層学習を分析ツールとして用い,これまで実験的検討が困難であった暗黙的な視覚特徴の役割を明らかにすることを目指す。まず深層学習を用いてブランドらしさに寄与する視覚的特徴を網羅的に抽出し定量化する。続く心理実験において,それらの特徴の強度を実験的に操作し,ブランドらしさの認知および注視点/注視時間/視線移動等を測定する。
1.応募状況
2024年11月30日を申込締切日(当日消印有効)として募集し,期日までに3名の応募がありました。審査希望部門は第1部門(原理・認知・感情)が1件,第2部門(教育・発達・人格)が1件,第3部門(臨床・福祉・相談)が1件となりました。
2.選考委員会
若手会員研究奨励賞規程に基づき,選考委員として委員長 (上瀬由美子常任理事 学会活性・研究支援担当)の他,常任理事2名(来田宣幸氏・軽部幸浩氏),委員長指名による委員1名(古屋健氏)の,計4名が選出されました。選考委員には委員長より,予備審査として資料(応募者が提出した研究計画書と研究業績1点をPDF化したもの(匿名化済))を送付し,委員長宛に審査結果を返送するよう求めました。
3.評価基準
応募書類は以下の4つの観点について「5:優れている-3:基準を満たしている-1:不十分である」の5段階で評価されました。
(1) 研究課題の学術的重要性・妥当性(「研究目的」欄など)
(2) 研究計画・方法の妥当性(「研究計画・方法」欄など)
(3) 研究課題の独創性及び革新性(「研究目的」「研究計画・方法」「研究の独創性・意義」欄)
(4) 研究遂行能力の適切性(添付業績など)
4.選考経過
2025年2月に選考会議が開かれました。まず委員長によってまとめられた予備審査の結果(全体集計)が提示され,観点別評定合計点の平均は最上位者15点,2位14.25点,3位14点と拮抗していました。続いて委員長より選考委員より提出されたコメントについて説明されました。いずれの申請についても研究計画の不十分さや課題が指摘されている一方,社会的貢献が期待できる点や若手らしい挑戦的な研究であるといった評価がなされていました。これをふまえて慎重に審議した結果,全員一致で,3名全員を奨励賞受賞の候補者として推薦することが決定しました。
5.講評
今年度申請された研究の評価はいずれも観点別得点の平均が全て「3」以上,総合得点も14点?15点と高く拮抗しており,審査の結果,3名全員が受賞することとなりました。
受賞研究に対する委員の評価の一部を紹介します。まず楊帆氏の申請については,現代社会の心理的健康課題に応える重要な提案であり,学術的および社会的貢献が期待される点が評価されました。今後の期待・課題として委員からは,セルフコーチングの内容やオンライン募集に伴う課題への対応が具体化されることにより計画の実現性がさらに高まると考えられる,計画された両研究の関連を明確にする形で研究の遂行や論文化を進めてほしいといったコメントが出されました。
西堀まゆ氏の申請については,個人の経験や文化的・社会的背景を考慮してキャリア形成プロセスの個別性と普遍性を明らかにする視点が意義深いこと,対象者へのインタビューを通じて得られる質的データの詳細な分析が計画されており実行可能性も高いことが評価されました。今後の期待・課題として委員からは,対象者数の少なさに伴うデータの一般化可能性の限界があるため,この点を課題として意識しながら研究を進めてほしいといったコメントが出されました。
下條朝也氏の申請については,視覚的特徴の抽出と心理的効果の実験的検証を組み合わせる点に新規性が高く,理論的および実務的な応用可能性を有しているが評価されました。今後の期待・課題として委員からは,深層学習によるAIの判別過程では人間のそれとは全く異なる処理がなされるので具体的な分析方法の開発が求められる,AIの判別モデルは学習フェーズでの学習用データに大きく依存する可能性があり結果をどこまで一般化できるのか慎重に検討してほしいといったコメントが出されました。
今年度の申し込み件数は3名にとどまりました。8月の大会がオンライン開催となり,計画されていた本賞の会場での宣伝が実施できなかった点も一因と考えています。応募資格をもつ若手研究者の数は限定されますが,委員会としてはこの賞の認知度アップについてさらに工夫を検討したいと考えています。
なお奨励賞受賞者の方は,受賞の翌年度あるいは翌々年度の応心大会で研究成果を発表する義務を有します。応募する方はこの点をご確認いただいた上で申請してください。また,受賞された方には義務となる大会発表後,ぜひ成果を「応用心理学研究」への投稿にもつなげていただけるようお願いいたします。
 日本応用心理学会
日本応用心理学会