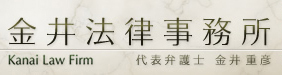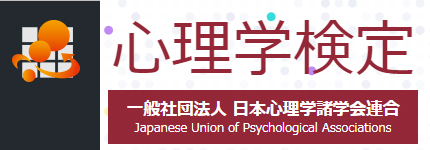理事長 田中 真介(たなか しんすけ)
京都大学
●はじめに
新緑の季節,いかがお過ごしでしょうか。日本応用心理学会(The Japan Association of Applied Psychology; JAAP。略称「応心」)は,本年4月より,新しい理事会・常任理事会をスタートしました。学会ホームページの「役員・事務局」欄をご覧ください。https://j-aap.jp/?page_id=62
2024年4月から2027年3月まで,新しい理事長として田中真介,副理事長として来田宣幸,また軽部幸浩が事務局長を担当し,常任理事10名,理事・推薦理事36名で本学会の活動を支えていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
●源流への信頼
1)1998年の秋に,私は初めて本学会の年次大会を準備する仕事に携わり,京都の龍谷大学大宮学舎で多くのみなさんをお迎えしました。田中昌人先生が大会委員長を担われた第65回大会です。その時以来,年次大会に参加するたびに,あたたかいアットホームな学会だなということをよく感じてきました。一つの学術分野の「学会」というと,通常の場合には,機関誌に論文を発表し,また年次大会や研究会でほぼ同じ専門分野の研究者が一堂に会して研究成果を発表して,互いに切磋琢磨しあう場であることは確かです。ですが「応心」はそれだけでない魅力をもっていることが,一度この学会の大会に参加されてみるとよくわかっていただけるように思います。
2)2000年代に入って,新しい理事会の制度が発足し,2003年4月に岡村一成先生が初代の理事長として着任されたとき,「伝統ある本学会の良さは,特定分野に偏らない,幅広い領域の研究者や実務家が家庭的雰囲気の中で,自由に議論し,交流が図られていることにあると思っております」と語っておられました。二代目の森下高治先生は,このあたたかさや連携は,「個人を超えた学際的な問題,他の領域の研究者とのリエゾン(liaison;連携)」を豊かに育むことにつながると提起されました。
また三代目の藤田主一先生は,「本学会は,アカデミックな雰囲気に加えて,会員相互の親和を大切にするという伝統があり」,それによって心理学の応用領域を網羅した本学会は,「基礎と応用との輻輳的な関係」を実現し,「基礎心理学と応用心理学とが互いに関係しあった最先端の研究・実践内容に触れることができます」との貴重なメッセージを発信されています。これは,会員同士のあたたかいつながりが,心理学の諸分野の新たな研究の発展につながるという重要な問題提起となっています。
近年のコロナ禍の状況の中でも,本学会が多彩な工夫をして会員同士のつながりを大切にし,一人ひとりの研究活動を支える工夫をしてきました。藤田先生からバトンを受け取られた古屋健先生は,本学会が100年近い歴史をもつ長寿の学会となっている理由として,応心には「人を育てる組織風土」があり,「新しい応用領域に挑戦する心理学者たちを積極的に応援し,若手・中堅会員の活躍の場を広げる」ことによって,本学会が長い歴史と伝統を育んでいると評価されていました。会員の多彩な研究を支える本学会の活動が,心理学諸分野の次の100年に向けての飛躍を準備することになっているように思います。
3)「応心」のもっている深いあたたかさと前向きな明るさは,基礎的な研究だけでなく,多彩な社会実践の活動と取り組む中で培われた応心独自の力かもしれません。そしてそれが多様な分野をつないで問題に新たな光をあてて解決の糸口を照らし出していく。本学会のこうした不思議な魅力はどこから湧き出てきているのでしょう。とくに現実の社会の中でもっとも立場の弱い人たち,気持ちを言葉で表すことが苦手な子どもたちを優しく包み込むような雰囲気をもつこの学会には,そのようにいろんな人たちを支え励ます根源的な力が脈々と受け継がれ,また新たに生み出され育まれているように感じます。
私は,本学会を通じて共同研究に取り組み,また年次大会に参加する中で,相手を励ますそのような温かな心の源泉が湧き出ている瞬間を何度も体感してきました。多彩な分野の先輩・同輩・若手の方々と出会って交流し,またこうしたあたたかな時空間との思いがけない出会いがあって,研究生活の中での新たな楽しみとなったように思います。
…
●人間のお風呂,人間の薬
このあたたかな雰囲気の大切さを,実社会の中で子どもたちを助ける活動の中で,肌で実感した経験があります。私がまだ駆け出しの頃のことですが,二人の恩師とともに,医療被害を受けた子どもたちの発達と療育の研究と,その家族の生活を支えるための新たな調査研究に取り組んでおりました。
1992年秋そして翌1993年1月に,大阪高等裁判所での予防接種被害集団訴訟の証人質問のために,京都大学の田中昌人先生と奥様の滋賀大学,田中杉恵先生の3人で京都から大阪に向かいました。お二人は,ワクチン接種によって重い副作用被害を受けた方たち22名全員の健康と発達の状況について実態調査と発達診断を実施され,予防接種の副作用で受けた発達上の障害が,通常の知的発達遅滞とは質的に異なることを立証されていました。被害を受けた子どもたちの家族の生活の困難さをとらえるために,一昼夜ビデオ映像記録を撮り続ける「24時間タイムスタディ」を行っておられたことも印象深く記憶しています。
大阪高裁に赴く前に,阪急梅田駅の2階にある喫茶店で一息入れて,当時新たに問題となっていたMMRワクチン(麻疹・おたふくかぜ・風疹の三種混合ワクチン)による被害事件(1989~1993年)の経過と状況を詳しく伺いました。被害の実態を知ったのはこの時が初めてでした。私自身,BCGワクチンによって重度の障害を受けた乳幼児の療育研究を担っており,被害の実情は体感していました。この時期すでにMMRによる被害は全国に広がっていたにもかかわらず,国は接種開始から4年目を迎えてもこの欠陥ワクチンを中止できずにいました。1993年の接種見合わせが決定されるまでに,全国で1~2歳児6名が死亡し,1754名が無菌性髄膜炎などの重篤な副作用に苦しむことになります。最近でも,2020年以降のコロナ禍のあと,2024年になっても7回目,8回目と継続されてしまっているコロナワクチンの接種によって,厚労省への報告数だけで2000名を超える死亡者と4万件に上る重篤な副作用被害が出ています(応用心理学のクロスロード,16号,pp.25-26)。
田中昌人先生は大阪高裁での証言の中で,ワクチンによって被害を受け重い疾患や障害を持つに到った方たちへの今後の療育のあり方について,「人間のお風呂」そして「人間の薬」が大事だとして,証人質問に答えて次のように話されました。裁判の速記録から要約して引用します。
「家の中で一人でできていることも,それをさらに家の外でその力が発揮できれば,さらによりよく生きることができますね。しかし,予防接種被害を受けた方たちには特にそこに援助が必要です。絶えず親しい人がついていくか,あるいはその人とつながりのある人が受け止めていて,よく人間のお風呂というんですけど,それがあって初めて,力が発揮できる。そういうことでの配慮が必要ですね。温かな,受容される人間関係によって支えられなければいけない。そのような介護を充実させるとともに,国が法制度を整えて被害者とその家族を支え,生涯にわたって必要かつ適切で心のこもった公的な救済をしていくことが大切です。」
「家庭の中だけでの療育では,発達的な貧しさが引き起こされがちです。力の発揮の場が1つだけであると,その人が持っている力を表せる場面が少ない。…決まりきったところで自分の持っている力を表すしかなくて,自分の力がほんとうに太っていく,普遍性をもっていくという条件がなくなっている。同じ寝たきりであっても,学校に行く,通所の授産施設に行く,といったことが可能となることによって,その一つの力が普遍性を持つ,普遍性への両足を持つことになります。具体的には,他の人が働きかけても,表情が出てきたりします。…家庭と違って,嫌だったら泣くでしょうし,お風呂へ入れてもらうときにも,親が入れるのとは違う入れ方によるいろんな受け止めができますね。あやしてもらったり,そのことによって,親御さんのほうも新たに新鮮な関係を作って,自分に,本人に携わるというふうに,両方が新鮮な関係を持って新しいつながりが作れるということですね。…ご両親や家族の方々というのは,かけがえのない人間の薬としての役割を果たされていると思います。」(応用心理学研究,38巻1号,pp.23-24)
どんなに重い疾患や障害を担っていても,温かい「人間のお風呂」,そして「人間の薬」が,子どもたちをそしてその家族を支える。その確信がここに述べられています。「温かな,受容される人間関係」,「かけがえのない両親や家族の存在」,そしてさらにそれが社会の中で普遍化することの大切さが提起されておりました。このような取り組み,こうした人間のあり方こそ,応心が青年期・成人期の人たちの生き方を支え励ますためにずっと挑戦し自らの中に培ってきた伝統の精神として,貴重なものなのではないかと感じています。
…
●歴史と課題
第2次世界大戦前の1927年に関西で「関西応用心理学会」第1回大会,関東では1931年に第1回「応用心理学会」大会が開催されました。1934年以降,隔年で合同大会を開催し,1936年の第2回合同大会で大会名を「日本応用心理学会」として現在に至っています。2022年秋には京都工芸繊維大学(来田宣幸委員長)で第88回,2023年夏の亜細亜大学(髙石光一委員長)で第89回大会,今年は奈良市の帝塚山大学(谷口淳一委員長)で第90回大会が開かれます。
日本応用心理学会の設立後,本学会を起点として,個別の各分野の心理学会が設立され発展していきました。一方で,実社会の多様な問題にアプローチするためには,特定分野だけでなく,関連領域との協働・連携が重要となるでしょう。本学会の会員の専門領域は多岐にわたっていますが,関連の深い分野をひとつにまとめて部門構成を行い,各部門の研究の充実・発展を促してきました。
〔応心の部門構成〕
①(第1部門)原理・認知・感情
②(第2部門)教育・発達・人格
③(第3部門)臨床・福祉・相談
④(第4部門)健康・看護・医療
⑤(第5部門)犯罪・社会・文化
⑥(第6部門)産業・交通・災害
⑦(第7部門)スポーツ・生理
本学会の研究活動は心理学の全領域を含むとともに,広く人文・社会科学,自然科学の各学術分野との連携も模索され,現実社会の問題をとらえた新たな共同の取り組みを構想してきました。応心という独特な学会は,心理学に限らず関連する多様な研究領域の「専門知」が交流する「学問的な広場」を作り出し,新たな「学術的な越境」を可能にする「総合知」,「学際知」,そして新時代の「教養知」を育む場となっています。
このような歴史と特色をもった本学会では,私たち自身が研究者としての「自己信頼性」を大切に育みながら「社会的交流性」の力を生成発展させ,自分自身の専門的・総合的な力を高め充実させていけるように,会員のみなさんの研究と社会実践活動を支援していきたいと考えています。とくにこの1年は,以下の3つの観点について議論を深めていきます。
- ①(研究基盤への支援)会員の研究・社会実践活動への支援策の拡充(特に若手研究者支援の充実)
- ②(研究交流への支援)論文投稿・研究発表への支援。公開シンポ・研修会での研究交流の活性化
- ③(社会活動への支援)委員会主催セミナーの構想と実践,国際学会への参加支援,専門資格の充実
本年4月からの3年間,会員のみなさんと一緒に,本学会の活動を楽しく,よりよいものにしていきたいと考えています。お気づきのことや新たなアイデアなど,学会事務局あてに遠慮なく率直にご連絡ください。この8月には,帝塚山大学での大会でみなさんとお会いできるのを楽しみにしております。
 日本応用心理学会
日本応用心理学会